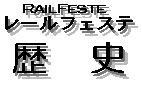
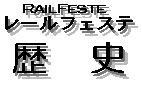
最初は1982(昭和57)年8月末に日本トレインクラブが、東京都清瀬市「清瀬こどもまつり」行事支援で行ったNゲージ鉄道模型展示からスタートしたレールフェステは、1983(昭和58)年8月から「レールフェステ」のタイトルで日本国有鉄道武蔵野線南流山駅のコンコースで開催、清瀬市こどもまつりのコンテンツに正式に記載されました。この時は未だレールをテーブルに仮設して、面積も3畳程度でしかなく、どちらかと言えば「鉄道模型運転」の域でしかありませんでした。
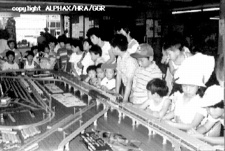 翌年1984(昭和59)年からは7月に国鉄南流山駅、8月に清瀬市民センターでの開催として例年行事となり、清瀬会場では最大16畳総延長221メートルの大レイアウト(仮設型では日本最大級)を実現して、その他鉄道資料の展示や模型教室も行い、流山会場では臨時の観光案内や国鉄職員によるオレンジカード販売等も加わり、イベントらしくなります。清瀬会場は85年が最後となりましたが、南流山会場はその後86年まで続き、代りに1987(昭和62)年からはJR東日本与野駅に舞台を移し、平成元(1989)年まで開催されました。
翌年1984(昭和59)年からは7月に国鉄南流山駅、8月に清瀬市民センターでの開催として例年行事となり、清瀬会場では最大16畳総延長221メートルの大レイアウト(仮設型では日本最大級)を実現して、その他鉄道資料の展示や模型教室も行い、流山会場では臨時の観光案内や国鉄職員によるオレンジカード販売等も加わり、イベントらしくなります。清瀬会場は85年が最後となりましたが、南流山会場はその後86年まで続き、代りに1987(昭和62)年からはJR東日本与野駅に舞台を移し、平成元(1989)年まで開催されました。
国鉄の分割民営化前後には、首都圏で多くの企画に参加或は主催して展開しましたが、1989(平成元)年以降は日本トレインクラブ・北海道鉄道研究会が団体専用臨時列車やC623機運行支援にシフトした為に、翌年から一時的に休止となりました。
この間にも模型の修理技術の研究の会合や、メンバーの自宅に集っての整備等は年2〜3度行われ、1996(平成8)年以降再びレールフェステは復活し、1999(平成10)年8月には9月に掛けて約一ヶ月間、JR東日本品川駅ホームで行われた催事に派出し、仮設型としては国内最長の展示を成し遂げました。
これを契機として青年文化連盟(当時)内でレールフェステをもっと地域に役立つ企画として展開出来ないかどうかの検討を始め、2001(平成12)年7月から既に具体的準備に入っていた特定非営利活動法人移行と重ね合わせて「交通公園の活性化支援の素材として」の位置付けで東京都足立区北鹿浜公園で実験的に開催、2002(平成14)年6月の特定非営利活動法人交通文化連盟設立に併せて資材と企画がそれまでの北海道鉄道研究会・青年文化連盟から交通文化連盟に移管され、2003(平成15)年3月の北鹿浜公園での開催以降、本格的に「交通公園の誘客」を主眼とした「定期的開催」を開始致しました。
そして、2004(平成16)年7月9日、足立区より協働事業として承認され、7月開催のステージから足立区共催となりました
(実績) −主催−(日本トレインクラブ・青年文化連盟主催のものも含む) 東京都足立区・北鹿浜公園(現在実施中) 千葉県流山市・国鉄南流山駅 埼玉県浦和市・JR東日本北浦和駅 埼玉県浦和市・JR東日本浦和駅 埼玉県与野市・JR東日本与野駅 千葉県松戸市・松戸市青少年センター 埼玉県浦和市・JR東日本南浦和駅 茨城県土浦市・JR東日本土浦駅 茨城県土浦市・ミニSL遊園 −応援・派遣−(東鉄サービス・銀河鉄道・日本国有鉄道等要請のものも含む) 東京都千代田区・神田区民センター「三町会合同こどもまつり」 千葉県松戸市・松戸市市民活動サポートセンター 千葉県流山市・杜のアトリエ黎明 茨城県ひたちなか市・JR東日本勝田電車区「勝田電車区まつり」 千葉県松戸市・新松戸市民センター「青年国際交流フェスティバル」 東京都清瀬市・清瀬市民センター「こどもまつり」 茨城県水戸市・JR東日本水戸駅「開業100年イベント」 東京都千代田区・大丸東京店 東京都台東区・JR東日本上野駅 東京都台東区・松坂屋上野店「青函トンネル開通記念物産展」 東京都千代田区・三越日本橋店 東京都港区・JR東日本品川駅「ドリームトレイン1999」 千葉県鎌ヶ谷市・鎌ヶ谷文化会館 埼玉県川口市・川口文化会館 北海道小樽市・JR北海道小樽運転所「シロクニまつり」 静岡県清水市・「市民まつり」
※太字は交通文化連盟となって以降の企画
|
|
|
|
|