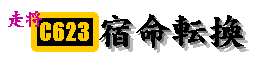
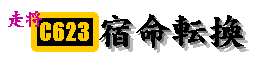
小樽築港機関区は国道5号バイパス(札樽自動車道接続点)の横にある。ドブ川を挟んで市道があり、函館本線があり、バイパスがある。木造二階建の質素な事務所の正面にC62の動輪が飾ってある。玄関を入り一階の事務室の片隅に企画室はあった。その鉄道電話が鳴った。
電話の相手は竹島紀元・鉄道ジャーナル社社長である。飾らない彼は「社長」では無く「編集長」の名刺を配る。配るのは名刺より「気遣い」の方が多い。
昭和46(1971)年に鉄道ジャーナル社が制作した記録映画「雪の行路」では、小樽築港機関区全面協力で見事な映像が撮影できた。大学の実習で故郷九州で蒸気機関車の添乗を経験し、ジャーナリストの道に入ってもその視点は「現場」にあった「常在現場」の人だった。
企画室が孤立化した事を心配して連絡をしたものだったが、事態は深刻だった。一国鉄職員の身分でC623機復活に限ってみても法制的・技術的対処解決は既に見ていた。「後は金だけ」と言う殆ど企画は完成の状態になっているにも関わらず、彼等の情熱は空転していた。
東京・飯田橋の古いビルの一角に「株式会社鉄道ジャーナル社」はあった。原稿や資料が机に「壁」を作る中に「編集長」の椅子はあった。竹島は別の電話を掛けていた。相手は日本国有鉄道常務理事・運転局長の山之内秀一郎だった。
「何とか、彼等の情熱をこのまま埋もれさせない様にして頂けないだろうか・・・」
 鉄道好きな眼鏡の学生の笑顔が竹島の脳裏にあった。2人は山之内が学生の頃からの付き合いだった。山之内も小樽築港機関区に縁があった。国鉄本社のキャリアとして就職し、実習で小樽築港機関区の扇形庫を駆け回った。騒然な庫内に高い声が良く通っていた・・・「シベリアオオカミ」とあだ名された山下仁郎の声だった。以来、毎年年賀状は欠かさなかった。二人は、直接会って支援策を練る事とした。
鉄道好きな眼鏡の学生の笑顔が竹島の脳裏にあった。2人は山之内が学生の頃からの付き合いだった。山之内も小樽築港機関区に縁があった。国鉄本社のキャリアとして就職し、実習で小樽築港機関区の扇形庫を駆け回った。騒然な庫内に高い声が良く通っていた・・・「シベリアオオカミ」とあだ名された山下仁郎の声だった。以来、毎年年賀状は欠かさなかった。二人は、直接会って支援策を練る事とした。
山之内は技術畑を歩んで、ATS(列車自動停止装置)の開発と改良に一貫して関わった。東北新幹線建設たけなわの頃には東京北鉄道管理局長として作業着にヘルメットで現場に度々足を運ぶ、根っからの技師だった。
運転畑の横山も義理と人情に厚い武将だった。上司の要請と言う切っ掛けもあったが、「一国鉄運転屋」として、彼に取っても必死に情熱を持ち夢を現実にしようとする部下が愛おしくもあり、掛け替えの無い人材である、とも認識していた。
資金以外でも未解決の問題は山積していた。C623機そのものの話である。
当時、北海道鉄道記念館は小樽市教育委員会小樽市博物館の所管する「博物館分館」的存在だった。一度は寄贈されたC623機を手宮から築港へ移すにはその所有権に関する協定が必要だった。
昭和61(1986)年4月16日、運転車両部と小樽市教育委員会はC623機の「貸与」と代換展示素材として32両の車両の「交換条約」を締結した。小樽市博物館(当時)は元日本郵船小樽支店として千島樺太交換条約の際に舞台ともなったが、その条約は時の海軍中将・全権大使の榎本武楊が締結を実現させた。幕末最後迄函館・五稜郭で幕臣の意地を見せた武将・榎本和泉守武揚である。その榎本が発見し有名になった「古代文字洞窟」の道を隔てた向いに北海道鉄道記念館はあった。
6月5日、苗穂工場の下請会社「札幌交通機械株式会社」から小樽築港機関区長宛に「本線旅客営業用復元工事」の見積書が届けられた。汽缶と車輪の削正等工費を除き、6740万円だった。
その直後、早朝のテレビにC623機が映った。札幌テレビ(NNN系列)ズームイン・朝!のワンコーナーだった。
「このSLを走らせたいんです!義援金をお願いします!」
往時の重連で深雪の峠を往くC62の姿が流れた。
その直後に工藤の許に一通の手紙が配達されて来た。差出人は「上島達司」とあった。神戸市のUCC・上島珈琲本社の社長からの、資金協力の意志を伝えるものだった。これを受けて6月19日、SL復活の会は大森義弘道総局長に正式にC623機復元の要請を行った。
「こんなのが走ったら、凄いですけれど、C62はもっと大きいんです。御存知ですか?」
彼は見学に来た一人の老人と思ってこんな事を言ったのだが、老人は
「C62ですか・・・」
「ええ、小樽のC623の走るのを見てみたいと思っておりまして・・・」
「君、面白そうな話ですね・・・ちょっと松澤君、彼を部屋へ・・・」
え?!
傍らの職員を呼んで、吉野は一つの部屋に案内された。「館長室」だった。身体中の毛穴が一斉に汗を吹出す感覚だけがあった。
案内をした職員は「副館長・松澤正二」と書かれた名刺を渡した。そして老人は「財団法人交通文化振興財団会長」と書かれた名刺を渡した・・・
吉野はあの夏の日にC623機と出会ってからC623機に取り憑かれてしまった。本当に本気の馬鹿になったのであった。日本トレインクラブの仲間達にC623機復活をぶち上げてやはり馬鹿!と言われたのだが、その11月28日には北海道鉄道研究部を立ち上げて、翌年には北海道鉄道研究会として独立して「C623機復活」をテーマとして追い掛けていた。仲間達は国鉄新規採用停止で国鉄を諦め、臨雇を去り民鉄に散ったが、吉野だけは最後まで国鉄と上野駅に留まりたい!と頑固だった。誰もが同じ気持ちではあったから、誰も説得も説教もしなかった。が、C623機だけは皆一様に諌めた。
「俺達に何が出来る?どんなに銭掛かるか知らないんだぜ」
「なら、銭の掛からないところで攻めるよ」
馬鹿は馬鹿でも、頑固な馬鹿だから、始末が悪かった。その馬鹿は恥も何も感じなかった。ただ一点「C623機の復活」しか見えなかった。で、SLに関わると聞けばそんな人物の元を尋ねた。
「馬鹿らしい、君の様な若者がSLだなんて子供じみた事を言うな!」
「これからはリニアモーターカーや新幹線の時代だ、蒸気機関車なんてナンセンスだ、無意味だ」
散々罵倒された。しかし、怯まなかった。むしろ罵倒されればその反論を一生懸命考えて、法律的と言われれば図書館に通い詰めてその突破口を探した。何時の間にか北海道鉄道研究会のメンバーは日本トレインクラブの幹部に重複していた。
その結論が、「鉄道輸送警備隊」だった。運行に際して最も危倶されるのは群集する鉄道マニアで、その警備は彼等の行動を警備会社や警察が把握しにくいだけに困難で、また警備費だけで復元費用に相当する事も解った。問題はそれに「悪戯」が横行している事だった。沿線で人の家の庭や畑を踏み荒らす、道路やレールにまで鈴生りになって列車を停めてしまう事もあったし、SLを撮る為に対向列車に接触して死亡する事件などもあった。SLにとって何よりの敵は「事故」だと認識した。であれば、ボランティアの警備チームを配置して事故や犯罪を防圧しよう、と考えたのだ。
それと並行して、SL企画のスタイルも研究していた。国鉄がこんな状態ではとてもSLなんて言い出せない、ならば民間主導の「主催型」=オーダーメイド列車で実施する方法は?となり、その実験としてその8月に北海道で団体専用臨時列車の運行の準備をしていたのだった。その資材を買いに行った秋葉原で交通博物館に立ち寄ったものである。
「君、頑張りなさいよ、夢をね、情熱を持って取り組む事はどんな事であれ、大事な事だから・・・走るよ、きっと、C623は。」
始めて同意の意見を聞いた。興奮した彼はその夜メンバーに電話を掛けまくっている。
「私も皆さんのSL復活の夢を信じてます!国鉄職員を代表して感謝と共に、是非その列車に乗務させて頂きたいと思います!」
とスピーチした。皆、輝いた笑顔に感激の涙が光っていた。
その翌日、彼等の一部は観光の為に小樽に来ていた。吉野は小樽築港機関区に立ち寄ると名刺を置いて来た。4月には小樽築港機関区に行き、渡部には会えなかったが、C623機復活の動きが本格化しているのを知っていたからである。団体専用臨時列車の窓口となった札幌旅行センターの高橋副所長や上砂川の佐藤駅長、道総局営業部の鈴木主幹、そして苗穂機関区の職員達等から断片的にも様々な情報を得ていたからである。
9月10日、吉野はそれまでの北海道鉄道研究会独自のC623機復活の構想を「意見書」として小樽築港機関区OBの吉田弘美を通じて復活の会に提出した。後日、これを読んだ工藤と渡部から現状とその熱い思いが綴られた手紙が鉄道事業郵便で彼の職場だった上野駅案内所に届けられた。(北海道鉄道研究会の構想は、単に蒸気機関車と列車についてのものではあったが、永く全国から小樽・倶知安と言う観光スポットに観光客を誘致する為に区間は小樽〜倶知安間で臨時快速とし、客車は在来型一般車5両程度でうち1両を食堂車(喫茶室併設のサロン)として地元の新鮮な乳製品や珈琲等が楽しめる、鉄道マニアも一般観光客もリピート化するハードを必要としている。この当時の復活の会の企画書では、札幌〜倶知安間で小樽〜倶知安間をC623機、札樽間を電気機関車として、客車は14系6両・種別は急行か特急としていた。)
その翌日の9月11日には苗穂工場の技術者が手宮に赴き、本格的に復元工事の体制が整った。その陰に横山部長の執念が垣間見える。
虚脱感は蔓延していた。不安は恐怖にもなり、閑職では無く「馘首対象者収容所」と目されていた「人材活用センター」ではその恐怖が爆発寸前だった。所長兼任の首席助役・越田亨はその抜殻同前の部下達を勇気づけて、誇りを持って国鉄小樽築港機関区人として新天地に新会社に移って欲しいと思っていた様である。以前より和田達の夢は知っていたので、陰日向に彼等を応援していた越田もC623機復活には熱い思いを秘めていた。
「そんな事やりたくねぇ、どうせクビになるんだ、俺達・・・」
具体的にC623機を手宮から移送し、その復活が確実に可能かどうかの復元調査工事をする、その段取りを取り決めている時の事である。
「敬吉よ、当局にそんな尻尾振ってまで残りたいか?」
越田は黙っていた。
「どうせクビならSLなんてしんどい事はしたくない・・・」
攻め立てるものの、台詞に勢いは無かった。と、突然越田は立ち上がって怒気を含んで大声で、しかし涙を浮かべて訴えた。
「君らも小樽築港機関区の人間だろう、国鉄の人間だろう!今ここにロクニが運ばれてくる、復活させる為にここに運んで来るんだ!鉄道屋の意地、誇りは何処に行った!?先輩達が築き上げた歴史を留める為のロクニなんだぞ!そんな逆境にあって夢も見れなくなったのか!我々築港機関区の意地を見せて、ロクニを甦らせるんだ!全員で・・・全員でだ!」
「よし!意地を見せてやるべぇ!」
一人が立ち上がった。
「俺もやるぞ!」
二人立ち、
「築港を舐めるな!だ!」
総員が立ち上がった。泣いていた。小樽築港機関区の宿命転換の瞬間だった。
|
|
|