鉄道車両(機材)分野は、船舶やバス、航空機より保存例が多く、現実に旅客営業している例も比較にならないものがあります。しかし、そんな鉄道機材でも、その殆どは「静態」つまり動かない(或は動けない)状況・環境に在ります。
従来の保存スタイルは
1・放置 廃棄又は解体待ちの状態にあるもの。
2・静態所有 金属部材の扱いとして所有されているもの。
3・静態管理 老朽化防止の為に給油等がされ、屋外等に展示された状態にあるもの。
4・静態展示 屋根等或は屋内に於て展示された状態にあるもの。
5・動態所有 自走の状態にあるもの或は自走出来る状態にあるもの。
6・動態展示 自走し、走行を公開・展示しているもの。
7・営業現用 旅客営業に供され、車藉を有して運転使用されているもの。
と7つに区分できます。また、7・営業現用のものも、
7-1・展示用線等特定の軌道で小規模に運行されるもの。
7-2・専用的に特定の路線や区間でのみ運転が出来るもの。
7-3・通常正規の仕様として営業運転に使用出来るもの。
と3つに区分されます。動態とされている機材はこの他に、法制上からの分類として、
甲・車藉、全般検査(車両検査)、蒸機の場合ボイラー検査で合格適格とされ、一定の日数定期或は定型的に運転されているもの。
乙・車藉、全般検査、蒸機の場合ボイラー検査で合格適格とされ、運転が出来るもの。
丙・車藉、蒸機の場合ボイラー検査で合格適格とされているが、旅客営業はしないもの。
丁・蒸機の場合ボイラー検査で合格適格とされていて、展示物として自走可能なもの。
と分類できます。また、現用機材として運転状態を保つ為に交換用部品を確保する為に同じ機材を「部品」(上表の2・静態所有)として所有する場合もあり、一言で「保存」と言いましても多岐に渡ります。従来の保存のスタイルとは、これでもお判り頂ける様に、「静態」は例数が多いものの簡単な分類で(殆どが静態管理か静態展示の状態)、「動態」は個々の機材や会社により異なると言う傾向にあります。
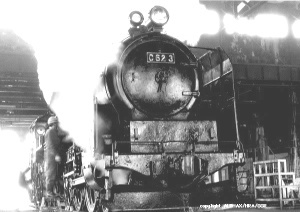 これは「動態」に要する費用・人材・手間が大きい為で、動態を実現し継続する為には費用は勿論なのですが、実は「人材=技術者」の確保と継続的配置が一番大きな問題となります。
これは「動態」に要する費用・人材・手間が大きい為で、動態を実現し継続する為には費用は勿論なのですが、実は「人材=技術者」の確保と継続的配置が一番大きな問題となります。
どうしても「機材」本体に目が行ってしまう、これは自然な事なのですが、実は「人」こそ「不可能を可能にする」キーワードなのです。
従来の保存スタイルで、今の処は個々に悩みや問題があるものの存置しておりますが、今後の展望を考える時、交通文化財に対する法制・税制上の抜本的改善や、国民の文化保存に対する意識の向上が無いままでは、極めて厳しい観測となります。
交通文化財は他の文化財に比べて、多角的に活用の可能性が秘められて居ります。特に建築物等が移動しない「点」の効果を造り出すのに対して、鉄道・船・自動車・飛行機は「線」の効果を造り出します。例えば、明治〜昭和期の「近代建築」の重厚な建物があったとして、観光客を誘引するのはその建物=点です。その周囲に同様な建物があり、散策等の提案をして観光誘引の起爆剤とすれば、それはただの点から「円」になります。蒸気機関車運行!となれば、始発駅と終点駅は「線」になります。その2つの駅の周囲に、御客様が地元の味覚や風景を楽しめるポイントが隣接していれば、蒸気機関車列車の乗客の多くを「来訪客」とする事ができます。しかし、その沿線や途中駅にポイントがあって、又は発掘して「途中下車の価値」を付加させられれば、線の途中に円が出来、それが沿線全体に拡がれば、「帯」に・・・つまり、蒸気機関車列車の直接的観光誘引効果「ポイント」が、「エリア」に拡がり、その「競走」が魅力的な観光誘引地域へと発展出来ると言うものです。
公園の片隅に置いてあるだけなら、ただの「展示物」、レールの上の文鎮です。しかし、汽笛を鳴らせば「珍しいもの」になり、動かせれば「見所」になり、旅客営業運転すれば「地域観光の目玉」に、そして地域の元気の素にする事ができるのです。
実際、現在全国で運行されている蒸気機関車で、元々鉄道会社が保管していて復元・運行となったのはJR西日本のC571機とC56160機の2つだけ、北海道から九州まで14両の蒸気機関車は「公園の片隅のレール上の文鎮」だったものなのです。
勿論、そればかりが活用の方法ではありません。同じ展示物でも、補修をしたり、保存を継続する市民ボランティア活動が中核となって、地域の催事の中心となるものや、函館では青函連絡船の保存と観光誘引の起爆剤にと行政とNPOが協調しチャレンジするもの、ガイドが付いて説明をしたり、保存施設を観光基地とする運動等多様な挑戦が行われております。
その活動には、地域や都道府県の枠を超えて、広いゾーンからボランティアや愛好家が集って参ります。それだけでもかなりの「誘引効果」なのですが、それを一歩深めて「地域観光活性化を主眼とした交通文化財の保存・活用」を提案しているのが、私達交通文化連盟なのです。
その地域や立地、文化財の種類により対応方法は実は多彩です。更にそれらの保存には確かな技術や経験は不可欠です。それを根底に、その町や村が、御近所がどんなスタイルであれば「元気になるのか」、それを真剣に考えなければ、「何処かの真似」をそっくりやっだけのコピーでは、実は「観光誘引」にはなりませんし、長続きもしません。
そして常に、永い時間で「もっと面白く!もっとワクワク!」を考えて行くシステムが無くては、北海道のC623機の実例の様に計画の破綻や「マンネリ」「飽き」による利用減少は以外にあっさりと、そして冷静に着実にやって来ます。
粘り強いだけでは駄目なのです。そこに「常に現状に満足しない」挑戦への姿勢と、子孫に継承させたい!との強い思い、何でも有りでは無く何が「適合」するかを分析し判断する冷徹な眼が、「交通文化財」を「観光経済活性化素材」に、「地域の元気の素」にする秘訣なのです。
|
|
|