鉄道輸送警備隊の組織は、交通文化連盟の本部外局として位置付けされていて、理事長が最高指揮権者、執行幕僚長がその総指揮者(実際活動の責任者)となって、他のセクションとは独立したものとなっております。
執行幕僚長の補佐役として、副幕僚長・参謀長があり、その他に個別部隊の指揮者と経験者により参謀や幕僚が在ります。この幹部隊員は「幕僚」と呼ばれ、専門的或は経験上から隊員の指導や派遣時の現場の取り纏め、執行幕僚長への意見具申や助言をします。
その下に実働部隊、となるのですが、ここでは2つに大別され、現場に派遣されて警備を行う「警備部隊」と、調査・情報収集・分析・連絡・事務を専門とする「内勤部隊」となっており、内勤部隊は隊員各自の自宅や事務所が任務場所となります。
(内勤の組織)
◯内務室(室長1名・兼任)
■内務科(現在事務局から出向兼務)
■特科(新選組プログラム担当)
◯情報調査室
■地域防犯掛/■情報通信掛/■特命調査掛
警備部隊は6名の隊員で一個とした「小隊」を中心に、複数「小隊」で警備隊(「中隊」)を構成しており、任用されると同時に小隊に配属されます。但し、この小隊は「グループ」としての意味合いで、小隊が派遣任命を受けたからと言って、会社や学校を休んで任務に就く、と言う固いものではありません。実際にイベントや企画列車で派遣される場合(不定期的任務)は、「機動警備隊」がその都度組成されて、現場に出掛けると言うシステムです。
(警備の組織)
○第一機動警備隊
(1個小隊/哨戒及び観光活性化関係)
○第二機動警備隊
(1個小隊/輸送及び催事警備担当)
●特科流山派遣隊
(常任者3名・他はその都度機動隊より抜粋して任命)
●足立派遣隊
(常任者3名・他はその都度機動隊より抜粋して任命)
これらの部隊(チーム)の指揮者は隊員の中から選抜されて任命されますが、鉄道輸送警備隊では警察や自衛隊等と異なり、その役職や担当する任務の重要度等から階級を付与する事としております。
法的には何の効力も無い階級(職級と呼びます。)ですが、鉄道輸送警備隊では重要で、階級により交通費等の補助の支給や職員の任用(但し、現在交通文化連盟では有償専従職員は設定されておりません。)が決められ、また責任者としての範囲もそれが一つの目安となっております。しかし、階級は試験や在籍時間では決められず、あくまでも任務時間と本人の度量・経験が判断基準です。年齢も学歴も性別も関係ありません。言うとすれば「気合」の問題でしょうか?
(職級)
(第一職)警士補
(第二職)警士
(第三職)警士正
(第四職)警士長
(第五職)主任補
(第六職)主任
(第七職)統括
(第八職)指令補
(第九職)指令
(第十職)指令正
(第十一職)指令長
(第十二職)総指令
例外として、(1)理事に任命された者は、第七職統括以上を付与する。(2)職員に任命された者は、第三職警士正以上を付与する。(3)社員及び応援ボランティアで任用される者は、任用以前の経験を通算して職級を任命する。(規約第十九条)とあり、また特定職と言い、鉄道職員や警察・消防・警備会社の勤務や医師・看護士、北海道鉄道研究会鉄道輸送警備隊の経験者が2年の任期で隊員の指導等に任る場合、会費等を免除して職級も個々に付与する制度もございます。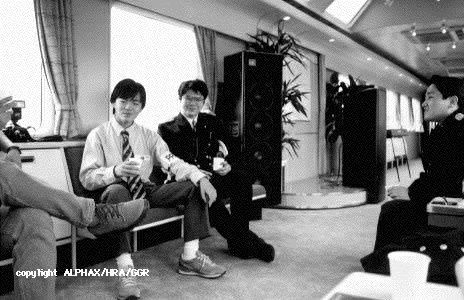
はっきり言って、疎外こそすれ賞賛される事など殆ど無かった「レールボランティア」時代、唯一の論功行賞がこの職級でしかなかったもので、警備ボランティアの苦難を物語る(?)「伝統」と思って下さいませ。
ただ、列車添乗や沿線警備では明確な指揮・命令系統の確立は文字どおり「生死」に関わる重大事で、その為にもこんな肩書が必要で、それが鉄道輸送警備隊の組織そのものと行っても過言ではありません。
|
|
|